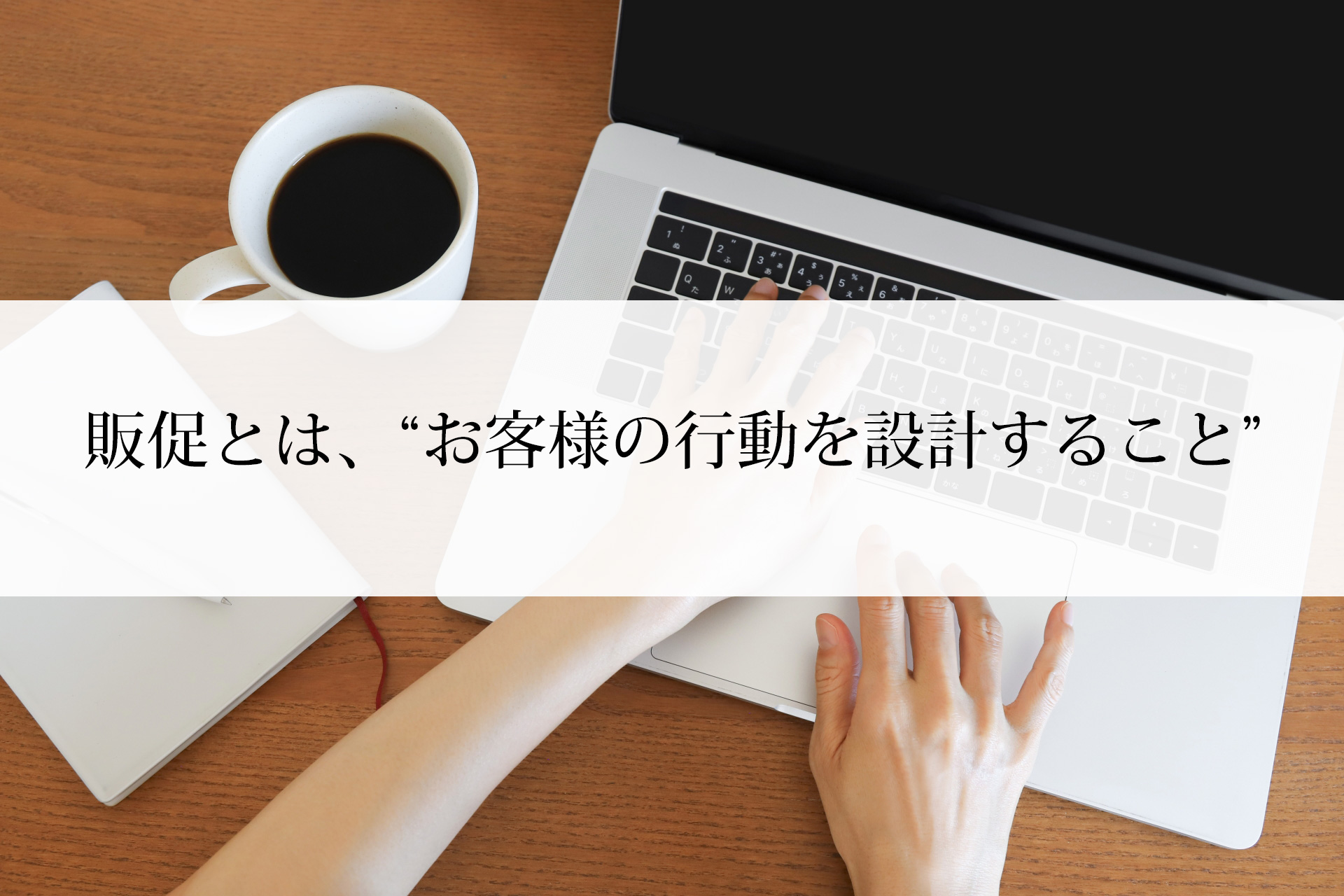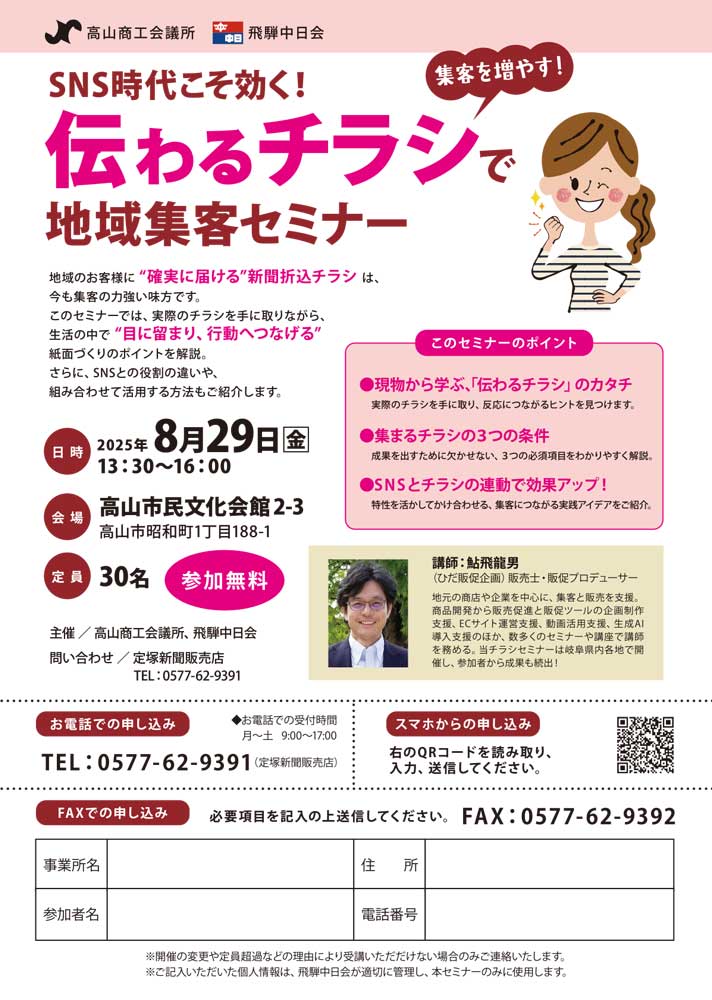GPT-5.1プロンプトガイドから見えてきた、ChatGPT“うまく使える”3つのコツ
2025-11-21

AIを使うとき、
「どう聞けばいいのか分からない」
「思った答えが返ってこない」
そんな声をよく耳にします。
実はこの悩み、GPT-5.1公式プロンプトガイドを読むと、
とてもシンプルな解決策に辿り着きます。
それは──
目次
“目的・材料・条件” の3つをそろえること。
これができれば、専門知識がなくても、誰でもAIを“使える味方”に変えられます。
■なぜ「目的」が大事なのか
AIは万能ではなく、“ユーザーの目的”を軸に動いています。
・何を作りたいのか
・何を知りたいのか
・どんな場面で使う情報なのか
ここが曖昧だと、答えがぼんやりしてしまう。
逆にいうと、目的を一行でも明確にすると、AIは一気に迷わなくなります。
例
×「キャッチコピー作って」
〇「チラシの見出しに使うキャッチコピーを作りたい」
わずかな違いですが、仕上がりはまったく別物になります。
■「材料」がないと一般論になる
公式ガイドで最も強調されているのが、**背景情報(材料)**の重要性です。
AIは「状況に合わせて回答を調整する能力」が高いのに、
材料がないとそれが発揮されません。
たとえば…
- どんな商品か
- 誰に向けた内容か
- どんな特徴や悩みがあるのか
たとえ短くても、これらの材料があればAIは“あなたの状況に合った答え”を返せるようになります。
例
「地元の高齢者が多い」「落ち着いた雰囲気を好む」
この一言があるだけで、文章の方向性が変わります。
■ 仕上がりを決めるのは「条件」
プロンプトガイドでは、
「出力形式を指定すると精度が一気に上がる」
と紹介されています。
- 文字数
- 文体
- トーン
- 箇条書きか文章か
- 表でほしいのか
これを指定するだけで、使いやすい文章に整います。
例
「100文字程度のやさしい口調で」
「表形式で3つにまとめて」
AIに迷わせない条件があると、読み手にそのまま渡せる品質になります。
■ “役割指定”は補助的に
「あなたはプロのライターです。」
という指示は、文章系では有効ですが、なくても成立します。
役割よりも
目的・材料・条件のほうが圧倒的に大事。
もし“表現が硬い”“読み手に刺さらない”と感じたら、
そこで初めて役割を追加すればOKです。
■ まとめ:AIを使いこなすコツは、難しくなくていい
GPT-5.1のプロンプトガイドが教えてくれたのは、
「特別な書き方」ではなく、人のコミュニケーションそのものです。
- 何がしたいか(目的)
- どんな状況か(材料)
- どう仕上げたいか(条件)
この3つがあれば、AIは驚くほど正確に動いてくれます。
ビギナーこそ、このシンプルな型が力になります。
むずかしいテクニックを覚えなくても、すぐに実務に役立つレベルが手に入ります。
ChatGPTを活用したセミナーを行っています。
- ChatGPTで心を動かすキャッチコピーを作ろう!
- SNS運用の強い味方!ChatGPTで魅力的な投稿を作ろう!
- Instagramでお客様の心を掴む ChatGPTで魅力的な投稿を作ろう!
その他の記事
(C) Hida-Sales Promotion & Planning